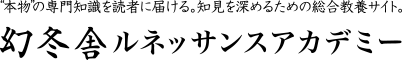連載
一覧細胞を科学する;棘皮動物ヒトデ胚の細胞研究は何を生み出すか【エピローグ】

金子 洋之(かねこ ひろゆき) 慶應義塾大学名誉教授
エピローグ
これ迄4回にわって、棘皮動物ヒトデの胚や幼生を研究材料に用いた細胞機能の研究を紹介してきた。研究成果としては、次の様に要約される。
(1)胚期の間充織細胞(MCs)は、細胞外マトリックス(ECM)の構築や再編成、上皮細胞(ECs)の増殖に関与
する、(2)幼生期には、MCsをはじめ種々の細胞が機能的に成熟し、幼生特有の免疫システムや神経システムなどを稼働させる、一方、(3)胚細胞は再構築能を有し、そこでは細胞選別や領域運命の変化を請け負う、(4)擬人的に細胞行動を捉えることで、細胞行動の目的を“細胞の意思”として明示できる。
これらは全て、共同研究の賜物であり、多くの研究者の方々や学生諸氏に心から感謝したい。約35年間を振り返って、アレコレあったなと感慨に浸り気味でもあるが、ヒトデは細胞機能の理解を深める上で有益な研究材料であることを再認識した。最近、イトマキヒトデの全ゲノムが解読された。これ迄は家内制手工業のように一歩ずつ進めていた分子的な解析も、遺伝子群のレパートリーやら発現動態まで全貌を一気に見渡せるレベルへと転換し始めている。ヒトデを用いた生命科学研究の新たな展開を期待する。
実験を行う研究者として、私自身は年齢的に幕引きの時期に来ている。私は、多くても3〜4名程度の学生指導の下で研究を進めてきた。このような場合、チームとしてはテーマを絞って、狭くて深くというやり方が普通である。私は真逆であり、浅くて広い研究スタイルでやってきた。ヒトデに焦点を絞っているとはいえ、実験を通して研究を進める以上、細胞機能の本質を統合的に理解するためには手を広げるやり方もありという気分であった。ただ、全てを捨ててでも本当にやりたいテーマを自身で見つけられなかったのかもしれない。遅かりし由良之助ではあるが、1本に絞ってやるべき価値があると今になって見えてきたテーマがある。それは、ヒトデ胚や幼生のMCsの進化的実体を明らかにすること、問いとしては「どうやって多細胞動物の身体の中に間葉系細胞は存在するようになったのか?」になる。ヒトデ胚で見出したMCsの突起を発達させた形態やネットワーク様の存在状態は、脊椎動物の結合組織の一員である繊維芽細胞とよく似ている(第1回の図2C参照)。一方、機能的側面は脊椎動物のマクロファージ的でもある(第2回の図2参照)。さらに、培養皿に降り立った際に多核体となり、基質を這う様相は、ある種の原生生物や粘菌のアメーバ状態とイメージが重なる(第1回の図2B参照)。原始地球における多細胞動物の進化過程を辿る様に、ヒトデ胚に見られるMCsは間葉系細胞の多くの特性を併せ持っている。……ということは、元々はアメーバだった?間葉系細胞の機能進化を理解する上で、ヒトデ胚MCsは重要な立ち位置にいるという気が強くする。
プロローグの項で述べた様に私自身の研究体験や感慨を少し披露したい。学部〜大学院時代には、プロフェッショナルである指導教官とアマチュアである学生(弟子)の有り様の洗礼を受けた。指導教官たちは弟子が下手を打てば容赦なく叱り飛ばし、ハードルを越えたら心から一緒に喜んでくれた。ここに、研究室における精神的なメリハリの実態を体験した。また、考えに考えて得た仮説を見切る潔さなども教示された(いつでも捨てることは出来るので持っておけと言われることもあり、結局どっちにすれば良いのか困ったこともあったが……)。大学院修了後、大学教員としての立ち位置に変わったが、研究者としての切磋琢磨はここから本格的に始まる。大学勤務では、殆どの場合は助手からスタートする。仲間となった先輩の研究者から、何を吸収するかは大事であるが、その内容はケースバイケースとなる。私の場合、研究者としての生活サイクルのみならず、大学だけでなく組織や社会につきものの多種多様な軋轢を真に受けない図太さ、伸び伸びとやることの重要さ等を生で見た気がする。また、私自身は、最初に勤務した大学から別の大学へ転出した。これに伴い、研究できる環境を再構築しなければならなくなった。大ごとであった。しかしながら、新たな研究者との出会いにより、今まで突破できなかった研究の壁に風穴が空いた。さらに、新規な共同研究も実現し始め、転出は良い結果に繋がった。大学教員には研究と教育以外の任務として、大学の自治への関与がある。これらをサボることは許されず、昇格に伴って多忙にならざるを得ない。この状態の中で、無駄を切り捨てることも必要となる。しかしながら、時間に吝嗇になることは必ずしも良い結果にならない。例え異分野であろうが、他の大学教員と面識を持つことで、研究する人生の多様さを客観的に捉えられる様になった。多くの研究者と付き合うことは誠に大事である。
最後に研究について私見を二つ書きたい。最初に、良い研究室とはどの様なものかという点である。結論から言うと、研究室全体が活性化しており、オープンマインドな空気感で満たされていることのように思う。そのためには、教員や学生を問わず研究室の構成員がそれぞれ独創的であることが鍵となる。“独創“とは、未知のアイデアを考え出すと捉えがちだが必ずしもそうではない。マジョリティーを構成する他者の言動を鵜呑みにせず、自身の中で本当にそうだろうかと問う姿勢である。研究分野にも流行りがあり、そこへの参入は決して悪いことではないが、独創性を持って対処しないと、流れに振り回されてしまう危険がある。今まで関与してきた国内外の研究室で、独創性を有した研究者と出会い、視界が開ける感覚を何度も味わった。また、研究の世界でも数多の競争はある。レベルが高いと感じる研究室では、競争はスポーツの如く自由闊達であり、悪影響としての秘密主義や傲慢さを内包する閉塞感は微塵も感じなかった。実際、メンバーが日々切磋琢磨している中でも風通しが頗る良く、大らかさを感じさせる独特の雰囲気があった。構成メンバーが、真のプライドを持ち、老いも若くも懐が深いことも共通している。ただし良い研究室に籍を置いても素晴らしい研究成果が出る保証はない。ただ、本人に謙虚さがあれば人として育つ気がする。
二つ目は、基礎研究に従事する若手研究者の評価についてである。急速に発達する科学技術に後押しされるように、基礎研究も活況を呈している。但し、大いに気になることがある。当分野の将来を担う若手研究者に対し、業績数や獲得研究費を評価対象にし過ぎていないだろうか。確かに、この項目は研究者の実力を客観的に計る方法として十分に意味がある。一方、普及している有期雇用という形態の中で、5年間やそこらで研究成果を上げ、次に繋げるというペースを余儀なくされている若手研究者にとって、業績数と獲得研究費が一義的な評価対象となっている風潮は慣れてもいるだろうが、実際には精神的ストレスであると思われる。これでは、本当に良い研究ができる体制とは言えない。現時点で業績数と獲得研究費において後塵を拝しているが、良い研究を結実させる資質と実力を有する若手研究者はいる。彼らが正当に評価されず、次のステップへ進む上で不利な状況に陥るのは非常に惜しい。これを好転させ、真に有望な若手研究者が安心して活躍できるようにするためには、新たな視点を持った評価システムを作り出す必要がある。例えば、実績に直結しがちな研究テーマだけでなく、自身に関しての将来の研究構想や研究理念などのアイデアも文書化してもらい、研究者としての実力と資質を判断する手立てはどうだろう。評価する側のエネルギーも並大抵ではないと想像されるが、評価手段の見直しは重要な案件と考える。