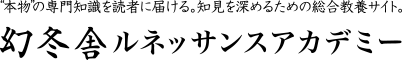連載
一覧「美しい国」の構造分析【第2回】―日本農村社会学再考―

中筋 直哉 (なかすじ なおや) 法政大学社会学部教授 地域社会学・都市社会学専攻
第2回:理論としての日本農村社会学
前回の議論に2点補足しておきたい。1つめは、日本の社会学がM.ウェーバーの社会学に「汚染されている」と述べたことについてである。私が言いたいのは、ウェーバーのような、西欧近代社会中心の歴史観と、社会的事実を個人の精神と行為に還元する方法のセットではない社会学を構想することが可能だし、有用かもしれないのに、日本に限らず、20世紀後半以降の社会学者にとって、それはまるで超自我に抗うのが難しいように困難だ、ということだ。日本農村社会学はそこから脱出する鍵となるのではないか。
もう1つは、草創期の日本農村社会学が柳田国男の影響を強く受けていたと述べたが、日本農村社会学は柳田民俗学でも、現在の民俗学でもなかったということである。日本農村社会学は柳田という「父」から自立する過程で形成されたのだし、現在の民俗学は日本農村社会学とは(柳田民俗学とも)ほぼ無関係に行われている。そのことは現在の民俗学の研究拠点の1つである国立歴史民俗博物館の展示を見れば明らかだ。
さて、今回は日本農村社会学がどのような社会理論を確立したか、鈴木栄太郎、有賀喜左衛門、福武直の3人の順に見ていきたい。とくに注目したいのは、彼らがどのような方法で社会的事実を捉え、どのような理論モデルを構築したか、である。
鈴木栄太郎が『日本農村社会学原理』(1940)で展開した社会理論は、「自然村理論」と呼び慣わされている。実はこの自然という語が誤解を招きがちだ。鈴木はけっして日本の村が自然にできたとも、自然に維持されているとも言っていない。今の世界標準の社会学の用語を使えば「下からの(from below)」といった意味だけを含ませている。それは上位の政治体から与えられた「行政村」と対をなす用語なのである。
「自然村理論」は、その前に調査された事実と、その後に与えられた説明とのセットではじめて理解できるものである。すなわち鈴木は、本州の多くの村には、より小さな地理的範囲に集まり(小字と呼ばれる)、主に血縁関係によって結ばれた、相互扶助のための家々の集まりと、国家によってより大きな地理的範囲が定められ、その統治のための地方政府(これが行政村)との間に、中くらいの地理的範囲を持った社会があって、村びとたちは自分たちの精神と行為を通してそれを保持しており、それが自然村だというのである。
では、なぜ村びとたちはこの社会を保持しているのか。村びと一人ひとり、あるいは家々は自らの私益を追求するが、行き過ぎれば互いの利益を奪い合い、存在を破壊しかねない。私益追求を統制し、公益追求に切り替える制度が必要だが、それを(ホッブズのリヴァイアサンのように)暴力的に外挿するのではなく、村仕事や村祭りといった、それ自体が公益追求を目的する共同行為への全員参加を通して教育的に内生させていく。その結果村びと一人ひとりの内面に埋め込まれる、公益と私益をバランスさせる思考回路を、鈴木は「村の精神」と呼んだ。この精神の核心は永続性である。村の永続が家々の経営の永続、村びとの生活の永続を保証する。村仕事や村祭りは、表面的な目的以上に、村の永続と私益の統制を象徴化した儀礼的行為なのであり、自然どころか、村びと全員に強制されることにこそ意義があるのだ。
こうした鈴木の議論に早くから疑問を抱いたのが、有賀喜左衛門である。有賀の疑問は、鈴木のいう自然村もまた外挿的制度ではないのか。村びとたちは自分で自分を縛らないと社会を構築できないのか、そうではないだろう、というものだった。だから有賀は、鈴木にとっては私益の集合態でしかない家の社会性の方に関心を集中させていったのである。
有賀にとって村びとたちの家は、独りでは生きていけないことを深く自覚した村びとたちが「下から」創り出す基礎的社会組織である。その目的は協力して生産し、消費し、成員の福祉を実現すること、すなわち共同生活であって、血統の継承や資産の分配と相続は二義的なものに過ぎない。だから家は、血縁関係に基づく家族や親族組織を内包するものの、それらにとどまらない広がりと柔軟性を持つのである。
生活が第一目的なのだから、それが困難なとき、家は成員に厳しくなり、それが容易なとき、家は成員に甘くなる。前者の場合、家は内側も他の家々との関係も支配従属関係を強めて一団となる。これを有賀は同族と呼ぶ。後者の場合家は内側も他の家々との関係も水平的に散開する。これを有賀は組と呼ぶ。村が置かれた政治経済環境の浮沈に合わせて、家々は同族に寄り集まったり、組に散らばったりする。これが同族と組の循環理論である。
また家の内側や家々をまとめる支配従属関係、有賀のいう親分子分関係は、組織全体の存続、向上が目的なのだから、上位者は一方的暴力や専制を行えず、組織のエージェントか調整役に過ぎなくなる。それゆえ家は企業や官僚制機構にならず、共同体の雰囲気を濃く漂わせるのである。
有賀のいう家々にとって、村はときどきの上位の政治体が住民管理や動員、徴税や土地管理のために下げ渡してくる外挿的制度に過ぎない。その村をも、村びとたちは、家的な関係で埋め尽くして、家の論理で制御し、外の政治体からの自立を確保していくのである。