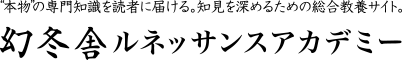連載
一覧科学を統治する市民を育てる【第2回】 トランスサイエンス問題と科学教育

荻原 彰(おぎはら あきら) 三重大学 教育学部
トランスサイエンス問題と科学教育
福島第一原発の事故以降、放射線とその健康影響に関心が集まっているが、中でも、「いったい年間どのくらいの量の放射線を受けると危険なのか」、つまり安全と危険の境界線はどこかということに人々の関心は集中している。しかし、放射線の場合、「一定量の放射線を受けると、皮膚障害などの影響が必ず現れる」確定的影響ならばこのような境界線を引くことができるが、がん(白血病などを含む)の発病確率を上げる確率的影響には境界線を引くことはできないとされている。
ではメディアでしばしば取り上げられる年間20mSv(避難指示解除の基準)とか年間1mSv(公衆、つまり一般人の線量限度)とはどのような意味なのだろうか。結論を言えばこれは安全と危険の境界線ではなく、交通事故など他のリスクとのバランスも考慮したうえでの受忍限度(容認できる限度)である。具体的に言えば、たとえば年間1mSvというのは年2万人に一人のがん死亡リスク、20 mSvは年1000人に一人のがん死亡リスクに当たる。この程度のリスクならば社会的に受容可能というのがICRP(国際放射線防護委員会)の判断であり、日本政府もこの基準を採用している(ただし福島の原発事故被災地域では、避難指示解除基準が20mSvであるため、公衆の線量限度も事実上20mSvとなっている)。
リスクの算出は科学に依存しているが、そのリスクを容認できるかどうかは科学の決めるべき問題ではない。それを決めるのは社会である。丸川珠代元環境相が1mSvの基準について「何の科学的根拠もなく」と発言したのはおそらくこの辺の事情を官僚に説明され、誤解した結果だと思われるが、リスクを容認する基準を決めるのが科学ではなく社会だという意味では、半分正しいとも言える。
このような問題は原発に限られたことではない。国土交通省は都市水害を防ぐために高規格堤防(スーパー堤防)の建設を淀川河口、荒川下流などで進めている。これらの堤防がどの程度の洪水に耐えられるのか、それは何年に一度の洪水なのか、生物相にどのような影響を与えるのかということはある程度科学的に答えることができる。しかし高規格堤防を建設すべきかどうかという判断は、対象地域の関係者に与える経済的・社会的な正負の影響を考慮に入れて行わねばならず、これは科学では答えられない問題である。
このように「科学に問うことはできるが、科学が答えることはできない問い」が存在することを指摘し、それをトランス・サイエンス問題と呼んだのがアルヴィン・ワインバーグという核物理学者である。トランス・サイエンス問題は科学と社会の界面に生じてくる問題であり、科学に助言を求めることはできても、社会がどう対処すべきか(被曝の基準の決定、堤防建設の決定)を科学が決めることはできない。社会が決めなければならないのである。
ここまでの筋立ては多くの人々が同意できることであろう。しかし、その先に一歩踏み込むと、とたんに視界は不透明になる。いったい社会とはだれのことなのか、社会の意思を集約する適正な手続きはどうあるべきなのか、社会の意思を表すのが議会制民主主義であるとすれば、政治家が決めていけばいい話なのか、そうだとした場合、そもそも政治家はこのような問題を判断する能力を基準として選ばれているのか、地域社会の民意と国全体の民意が異なるときにはどう判断すればいいのか(基地や原発の立地の場合はしばしばこのようなことが起こる)等々、雲のように疑問が次々に生まれてくる。
しかし、これらの問いにどのように答えを出すとしても、共通して言えることは、民主主義を基本原理とする社会においては、社会の意思決定は特定の集団の内部で閉鎖的に行われるべきではなく、何らかの形で国民または地域住民(以下、一括して市民と言うことにする)の民意を集約すべきであるということと、民意が適切なものとなるためには、意思決定の対象となる問題に対して、市民が判断できるだけのリテラシーと判断しようとする意思を持つ必要があるということであろう。前回のブログに倣っていうならば、市民が賢人になることがトランス・サイエンス問題を社会が扱う際の必要条件となるのである。つまり市民教育が決定的に重要だということだ。
さてそのように理解したうえで、初等中等教育を見てみると、現在の科学教育の不十分な点が露(あらわ)になる。驚くべきことに、初等中等教育はそもそも科学教育の主たるターゲットとして市民を考えていない。高度科学技術国家たる日本の科学技術を支える優秀な科学技術の専門家を多数輩出することが科学教育のもっとも重要な目的となっており、児童生徒はもっぱら科学技術人材をくみ上げるプールとして考えられている。優秀な専門家を多数輩出するために、広範な児童生徒に科学教育を施し、その中から優秀な人材を選抜していくのが初等中等教育における科学教育の主たる役割となっている。初等中等教育の科学教育(数学を含む)の内容は科学者・技術者になることを目的として設定されており、非専門家(市民、なお科学者・技術者であっても専門外のことでは市民となる)になることはそれ独自の意味を付与されず、副次的な目的と考えられ、専門家への道からそれた、いわば脇道としての扱いを受けているのである。
したがって、理科教育の主要な内容は大学で専門的な教育を受けるために高校まででどこまで履修しておくべきかという観点から決定され、トランスサイエンス問題が扱われる場合もあるが、それは付加的な扱い、いわば調味料にとどまっている。もちろん、初等中等教育が専門家養成の基礎という役割を担っていることを否定するつもりはない。しかし、初等中等教育が担う市民の共通教養を育てるという使命を考えれば、そこでの科学教育の、より重要な使命は、社会的に重要で科学だけでは決定できない問題であるトランスサイエンス問題を考え、判断することのできる市民を育成することであろう。教育課程はこの目的にそって編成されるべきであり、科学技術の専門家養成のための予備教育はむしろ付加的なものであるべきだと私は考える。